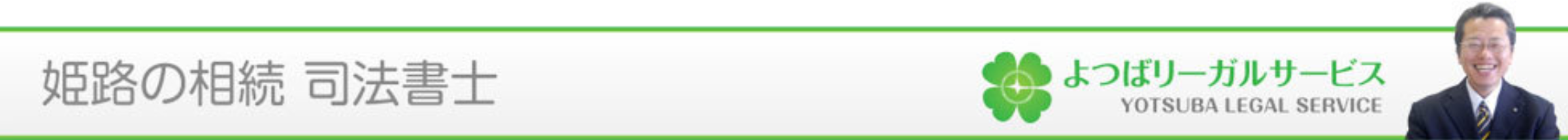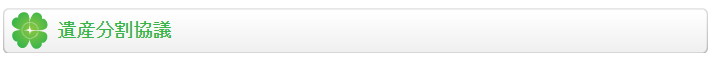相続相談を姫路でするなら、相続専門の司法書士【よつばリーガルサービス】
ご自宅へ出張相談も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
相続相談を姫路でするなら相続専門家、司法書士、よつばリーガルサービスへ。
相続手続き、相続登記、遺言作成、遺産分割協議などの相続相談の専門家です。
(業務エリア:姫路市、加古川市、高砂市、太子町、たつの市、赤穂市、福崎町、市川町、
神河町、加西市、小野市、加東市、三木市)
〒670-0949 兵庫県姫路市三左衛門堀東の町227-124
Tel.079-280-8884 Fax.079-280-8885
E-mail. obata0701@nifty.com
Q1 相続人に未成年者がいる場合、どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

A1 未成年者は遺産分割協議できません。
父、もしくは、母が存在するが相続人ではない場合には、その父、もしくは母が未成年者を代理して遺産分割協議に参加できます。
ただし、未成年者が2人いる場合には、それそれの未成年者に特別代理人を選任する必要があります。
そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法826条)。
つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。
特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。
申立に必要な書類は下記のとおりです。
・申立書1通
・申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
・特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
申立に必要な費用
・子1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
詳しくは、事前に家庭裁判所に確認しましょう。

Q2 相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

A2 遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。
まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に
不在者の財産管理人の選任の申立を行い、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。
不在者の財産管理人の申立に必要な書類は下記のとおりです。
・ 申立書1通
・ 申立人、不在者の戸籍謄本各1通
・ 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
・ 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・ 利害関係を証する資料
・ 財産目録、不動産登記簿謄本各1通
・ 収入印紙800円
・ 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります
詳しくは、事前に家庭裁判所に確認しましょう。

Q3 遺産分割後、認知されて相続人が新たに現れた場合、遺産分割協議は無効となりますか?

A3 相続開始後、すでに遺産分割その他の処分をした時は、その後、死後認知されて相続人となっても、その遺産分割は無効となりません。
認知により相続人となった者は、価額のみによる支払い請求できるだけです(民法910条)。
つまり、遺産分割協議で、相続財産を売却し換価分割した場合、その相続財産の売却は無効とはなりません。
これは、非嫡出子と遺産分割の安定性の調和を図ったものです。
そこで、遺産分割後、離婚の無効や、離縁の無効を主張する相続人が現れた場合に、民法910条が適用され、価額支払い請求権のみ認められるか、問題となりますが、民法910条は、共同相続人の既得権と被認知者の保護を図る規定であることから、新たに判明した相続人は、価額支払い請求権にとどまらず、再分割請求できるとする判例があります(最判昭和54.3.23同旨)
もっとも、このように解しても、第三取得者は、民法94条第2項類推適用によって保護されることも考えられます

Q4 相続人に認知症で協議できないものがいる場合どうしたらいいですか?

A4 一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
一時的にも意識が回復することがない場合は、成年後見人の選任を裁判所に申し立て
その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

Q5 有効に成立した遺産分割協議をやり直すことは可能でしょうか?

A5 遺産分割協議につき、無効原因または取消原因が存在するときは、共同相続人は
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることによって遺産分割のやり直しを
請求することができます。
無効原因や取消原因がない場合でも、共同相続人全員の合意があれば遺産分割
のやり直しをすることは可能です。
ただし、遺産分割のやり直しを行い、これによって各相続人の取得する財産の内容が
変更されると、税務署がこれを共同相続人間の実質的な贈与とみなし、多額の贈与
税が課税されるおそれがありますので、安易に遺産分割協議のやり直しをされること
はお勧めできません。

Q6 相続人全員が納得している場合は、遺産分割協議は不要ですか?

A6 遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければ
ならないわけではありません。しかし、後々のトラブルを避けるためにも協議の
内容を明確にして書面に残したほうがいいです。
また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。
例えば、遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の名義変更には
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と遺産分割協議書が必要になります。

Q7 遺言書がでてきましたが相続人で話し合った結果、遺言書にかかれた内容と違う
遺産分割とする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?

A7 遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産分割
協議は可能です。ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。
遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければ
ならないわけではありません。しかし後々の紛争を避けることにも協議の内容
を明確にし書面に残した方がいいでしょう。

Q8 遺産分割協議終了後に遺産の漏れがわかったのですが、分割協議のやり
直しをすることはできますか?

A8 遺産分割協議に漏れた部分の相続財産は法定相続で共有していることに
なりますので全ての相続人で再度遺産分割協議をする必要があります。
遺産が不明の場合は、遺産分割協議書に『協議後存在が判明した全ての
相続財産は誰々に相続する』などという文言を入れ作成する事も可能です。

Q9 分割協議終了後に遺言書が発見されました。
分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が違っていました。
どうすればいいですか?

A9 遺言は、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言書が
でてきた場合は分割協議が無効になります。しかし相続人や受遺者が
遺言書の内容を確認の上、やり直しをしないことに同意すれば、あらためて
分割協議をやり直す必要はありません。

Q10 海外在住なので、印鑑証明書を貼付できないのですが?

A10 海外に居住されている方は、分割協議書に必要な実印や印鑑証明書というものを
利用することができませんので、それに替わる書類として居住地の日本領事館で
『サイン証明』を受けることが必要になります。